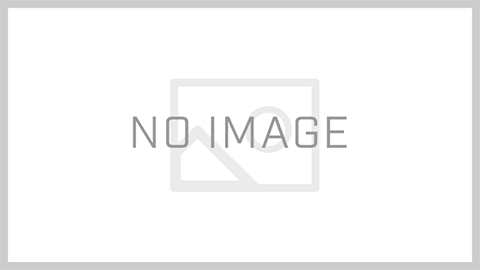訪問鍼灸マッサージと聞くと、患者様の自宅で施術を行う姿を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。ところがその裏には、施術者ならではの移動や働き方の苦労、工夫が隠されています。
近年、少子高齢化が進む中で、自宅で療養したいという高齢者のニーズは高まる一方です。訪問鍼灸マッサージは、そんな声に応える大切な存在となっています。しかしその一方で、施術者たちは移動距離や天候、時間管理など、日々さまざまな課題に向き合いながら仕事を続けています。
本記事では、訪問鍼灸マッサージに従事する施術者の声をもとに、移動手段や働き方の実態を詳しくお伝えします。普段は表に出ない現場のリアルを知ることで、訪問鍼灸マッサージの新たな一面が見えてくるかもしれません。
移動手段のリアルとは?自転車から車まで活用する日々

訪問鍼灸マッサージの施術者が最も頭を悩ませるのが「移動手段」です。患者様の家を次々と訪問するため、1日に5~10軒ほど移動することも珍しくありません。
都市部では、駐車スペースの問題や交通渋滞の影響から、自転車や電動自転車で訪問する施術者が多いといいます。特に東京23区内などでは、自転車が最も効率的という声がよく聞かれます。小回りが利き、時間に遅れずに回れるのが大きな利点です。
一方で、地方や郊外では車移動が主流です。移動距離が長く、一軒一軒が離れているため、車は欠かせない存在です。雨の日や猛暑の日でも荷物を濡らさず運べるのも車移動の強みといえるでしょう。
しかしながら、駐車場所が見つからない、自転車がパンクする、渋滞で訪問時間に間に合わないなど、移動にまつわるトラブルも少なくないようです。訪問鍼灸マッサージの施術者は、こうした移動リスクを常に頭に入れながら、効率よくスケジュールを組み立てています。
荷物の多さも悩みの種!道具を運ぶ工夫とは?

施術者が持ち歩く荷物は、見た目以上に多いのが実情です。鍼や消毒液、タオル類、マッサージオイル、施術ベッド、さらには書類や領収書類まで、必ず持参しなければならない物が多岐にわたります。
自転車の場合、後ろに大きな荷台を取り付けたり、前カゴを深めにしたりと、荷物を運ぶための工夫が欠かせません。中にはリュック型の鍼灸道具セットを使い、両手が空くようにしている施術者もいます。
車での移動であっても、荷物の積み下ろしは大変です。特に女性の施術者からは「折りたたみベッドを車に積むのが一番の重労働」という声が多く聞かれます。訪問件数が多いほど、車と患者様宅を何度も往復しなければならないため、体力的な負担は小さくありません。
とはいえ、道具を常に清潔に保つため、施術が終わるたびに消毒や整理整頓を徹底するのも施術者たちの日常です。患者様の安心につながる大切な仕事の一環といえるでしょう。
訪問時間の管理が働き方を左右する

訪問鍼灸マッサージの施術者にとって、時間管理は最重要課題の一つです。患者様ごとに訪問時間が決まっているため、遅刻は許されません。
しかし、移動中に予期せぬ渋滞や悪天候に見舞われることもあります。そうしたトラブルを避けるため、施術者は訪問先の順番や距離を綿密に計画します。実際には、患者様同士のご近所関係を考慮したり、訪問ルートを何パターンも想定したりする細やかな準備が必要です。
また、患者様の体調や事情によって施術時間が長引くこともあります。急な変更が起きると、次の訪問先への連絡や調整が必須となり、スマートフォンや連絡ノートが欠かせません。患者様の満足度を高めるには、施術の技術だけでなく、こうしたスケジュール管理能力が大きな武器になります。
訪問件数が多い日には、施術者が昼食を摂る時間すら取れないことも珍しくありません。体力勝負であることは間違いなく、健康管理もまた、施術者自身の課題といえるでしょう。
働き方は多様化!自由度と責任が表裏一体

訪問鍼灸マッサージの施術者は、個人で開業している人もいれば、治療院に所属している人もいます。働き方は多様化しており、どちらにもメリットと課題があります。
個人開業の場合、時間の自由度は高く、自分のペースでスケジュールを組めます。しかし、移動費や広告費、保険請求の事務処理など、すべてを自分でこなさなければならず、経営面での責任も大きいのが実情です。
一方、治療院に所属する場合は、訪問先の手配や保険請求の事務を会社が代行してくれるため、施術に集中しやすいという声も多いです。とはいえ、ノルマがあったり、スケジュールが詰まったりする場合もあり、体力的な負担は軽くありません。
近年は、ライフスタイルに合わせた働き方を模索する施術者も増えています。たとえば、週に3日だけ訪問を受け付け、残りは治療院勤務に充てるといった柔軟な働き方も見られるようになりました。
「訪問は大変だけれど、患者様から直接感謝の言葉をもらえることが、何よりのやりがい」という施術者の声が多いのも特徴です。現場でしか味わえない喜びが、訪問鍼灸マッサージを支えているといえるでしょう。
訪問鍼灸マッサージの未来に向けて

訪問鍼灸マッサージは、高齢化社会の中でますます求められる存在です。しかしその裏側には、移動の苦労や荷物の多さ、厳しい時間管理といった現場ならではの課題が数多く潜んでいます。
それでも、多くの施術者がこの仕事に誇りを持ち、患者様一人ひとりに寄り添いながら施術を続けています。今後は、訪問ルートの最適化や移動支援の仕組み、ICTの活用など、働きやすさを向上させる取り組みが期待されています。
訪問鍼灸マッサージの施術者たちは、地域医療の最前線で活躍する専門職です。移動の大変さも含めて、その仕事がどれほど価値あるものかを、多くの人に知っていただければと思います。
参考URL
- 厚生労働省「療養費の支給について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/ryouyouhi/index.html - 厚生労働省「地域包括ケアシステムとは」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html - 全国保険医団体連合会「療養費の取り扱い」
https://hodanren.doc-net.or.jp/hoken/ryoyohi.html - 日本鍼灸師会
https://www.harikyu.or.jp/ - 日本あん摩マッサージ指圧師会
https://www.zensin.or.jp/ - 東京都福祉保健局「訪問マッサージの保険適用について」
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/ryoyohi.html - 国立健康・栄養研究所「統合医療情報発信サイト」
https://www.ejim.ncgg.go.jp/ - 厚生労働省「医療従事者ナビ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052492.html