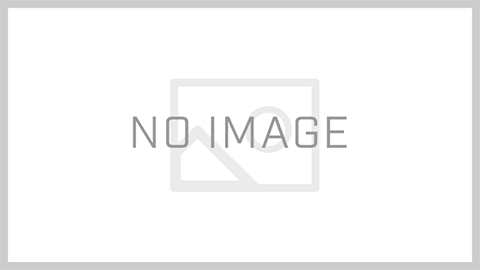「訪問鍼灸マッサージって、どんな人が利用できるの?」「寝たきりの親に使えるか知りたい」「手続きが複雑そうで不安」――このようなお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
たとえば、病気やけがで歩けなくなった高齢者が通院できず、家でのケアが必要になったとします。そんなときに役立つのが、訪問鍼灸マッサージです。医療保険が適用されるため、経済的な負担も抑えられます。
この記事では、訪問鍼灸マッサージの対象者や利用条件、適応する疾患、さらに申し込みから利用開始までの流れについて、詳しくお伝えします。
読後には、「自分や家族が使えるのかどうか」が明確に分かり、安心して手続きを進めることができるようになります。
さっそく、訪問鍼灸マッサージの対象となる人についてみていきましょう。
訪問鍼灸マッサージとは?対象者を解説

訪問鍼灸マッサージは、通院が困難な人のために、自宅や施設で施術を受けられる医療サービスです。
対象となるのは、日常的に歩行が困難な人です。
厚生労働省の定める基準によると、「疾病や傷病により歩行困難で、医師の同意がある場合」が対象とされています(※1)。これは高齢者に限らず、脳梗塞後遺症や関節リウマチ、重度の腰痛などで移動が制限されている人も含まれます。
たとえば、寝たきりの高齢者、骨折や手術後の回復期間にある人、脳卒中後で車椅子を使っている人などが該当します。
また、施設入所者であっても、医師の同意があり、外出が困難な場合は訪問が可能です。
訪問鍼灸マッサージは、ただのリラクゼーションではなく、治療目的の医療行為です。そのため、保険適用のためには一定の医療的判断が必要となります。
訪問鍼灸マッサージの利用条件とは?

訪問鍼灸マッサージを保険で利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
最大の条件は、「医師による同意書があること」です。
鍼灸の場合は「神経痛」「リウマチ」「頸腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」のいずれかの病名で、医師の同意が必要です。マッサージは「筋麻痺」や「関節拘縮」などの症状に対し、必要とされる場合に保険適用となります(※2)。
また、「歩行困難」が前提となるため、外出や通院が容易な人は対象になりません。家から一歩も出られない必要はありませんが、「通院が困難と医師が判断する程度」であれば対象になります。
加えて、介護保険と併用する場合は、担当のケアマネジャーと連携を取りながら調整を行うことが求められます。医療保険と介護保険の使い分けが必要になるため、事前にしっかり確認することが大切です。
訪問鍼灸マッサージの適応疾患とは?

訪問鍼灸マッサージは、慢性の痛みやしびれ、関節の動きの悪さなどを改善することを目的としています。
まず、鍼灸の保険適用疾患は、以下の6つに限られます(※3)。
- 神経痛(例:坐骨神経痛など)
- リウマチ
- 頸腕症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頸椎捻挫後遺症(むちうち)
いずれも慢性的な痛みやしびれがある状態で、医師が鍼灸施術を認めた場合に限られます。
次に、マッサージの対象となる症状は、「筋麻痺」「関節拘縮」など、身体の動きに障害が出ているケースです。これは病名ではなく「状態」に対しての適応となるのが特徴です。たとえば、脳卒中後の片麻痺や、長期間寝たきりによる関節のこわばりなどが該当します。
また、訪問施術では、パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症(ALS)、脊髄損傷後の後遺症など、難病に対しても症状に応じて施術が行われることがあります。
対象疾患は限定されますが、実際には「状態」を見て判断されることも多いため、まずは相談することが重要です。
訪問鍼灸マッサージの利用の流れとは?

訪問鍼灸マッサージを利用するには、いくつかのステップがあります。
最初に行うのは、「問い合わせと相談」です。利用を検討している場合は、地元の鍼灸マッサージ院や医療機関に相談しましょう。
次に、訪問マッサージの事業者がご自宅へ事前訪問を行い、本人の状態を確認したうえで施術内容の提案をします。その際に、同意書の取得についても案内されます。
その後、「主治医からの同意書を取得」します。病院の診察を受け、対象疾患であることと、訪問による必要性を医師が確認したうえで、同意書を発行してもらいます。
同意書がそろったら、いよいよ訪問施術の開始です。訪問頻度は週1~3回程度が一般的ですが、症状に応じて調整されます。
保険での施術となるため、定期的に同意書の更新(概ね3か月ごと)が必要となります。
まとめ
訪問鍼灸マッサージは、通院が困難な人のための保険適用サービスであり、医師の同意を得ることで自宅でも施術が受けられることをお伝えしました。
利用するには、医療的な条件を満たす必要があり、症状や状態によって適応かどうかが決まります。まずは信頼できる施術所や主治医に相談し、早めに準備を始めることが安心につながります。
※1 厚生労働省「医療保険における訪問鍼灸マッサージの取扱い」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/houmon.html
※2 一般社団法人 全国鍼灸マッサージ協会
https://www.zenshin.jp/use/houmon
※3 厚生労働省「はり・きゅうの療養費について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194157.html